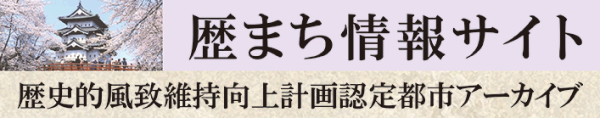里山の林床植物
里山で出会った林床植物
-

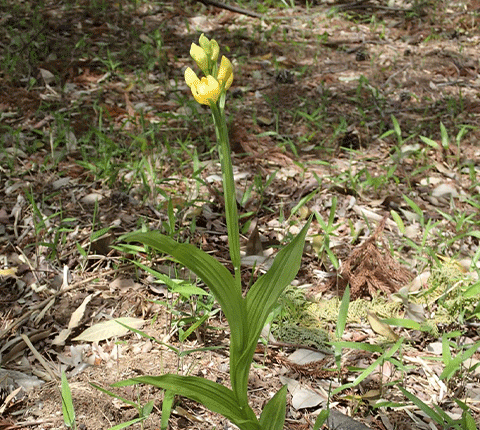
-

リュウキンカ
キンポウゲ科
和名は「立金花」で、茎が立ちあがり、金色の花をつけることから名づけられました。山地の日あたりが良い清流沿いの湿地に生え、雪融けとともに花が開きます。花びらのように見えるのは実は「がく」で、本当の花びらはもっていません。 -

イカリソウ
メギ科
和名は「碇草」で、碇(いかり)に似た姿の花をつけることから名づけられました。地下に長い茎を伸ばし、地上に葉を出して明るい雑木林の林床などに群生します。いかり型の花びらの長く突出した先端部分に蜜を蓄えており、これをトラマルハナバチがよく利用します。 -

チゴユリ
ユリ科
和名は「稚児百合」で、うつむいて咲く可憐で小さな花の姿形に由来するそうです。長い茎を地下に伸ばしており、春植物が終わる頃に地上に茎を伸ばして林床で群生します。多年草ですが、夏の終わりには親株が枯れてしまい、地下に残った茎の先端の芽からよく年新たな株が育ちます。 -

キクザキイチゲ
キンポウゲ科
和名は「菊咲一華」で、イチリンソウ(別名「一華草」いちげそう)の仲間で、花が菊に似ていることから名づけられました。花色は白から淡紫色まであり、様々な色のものが見られます。この種も花びらに見えるのは「がく」です。早春、林床に一面に咲く様子は見事ですが、一年のほとんどは落葉の下で過ごします。春早くに茎や葉を地上に出して花を咲かせ、ほんの2ヶ月ほどの間に光合成をして地下に栄養を蓄えます。初夏には果実を残して地上に出ている部分は枯れてしまいます。このような植物は「春植物」と呼ばれます。 -

クリンソウ
サクラソウ科
和名は「九輪草」で、いくつも重なって咲く花の様子が五重の塔の九輪を思わせるところから名づけられました。山地の渓流沿いの湿地や明るい林の中に群生します。春には、伸びた花茎の先に紅紫の花を咲かせます。