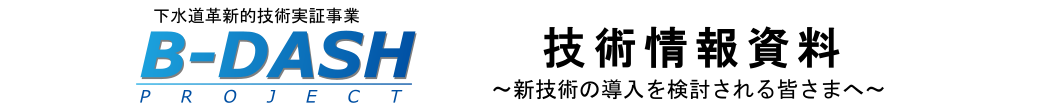下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)
技術情報資料【管路管理技術・浸水対策技術・その他】
- 全技術一覧
- 大規模処理場(50,000㎥/日以上)向け技術
- 中規模処理場(10,000~50,000㎥/日以上)向け技術
- 小規模処理場(10,000㎥/日以下)向け技術
管路管理技術・浸水対策技術・その他
【技術分野】| テーマ | 実証技術名(採択年度) |
|---|---|
| 管渠 マネジメント |
【高度な画像認識技術を活用した効率的な管路マネジメントシステム(H25)】 |
| 無停止での全周画像撮影により、現場調査時間を短縮! 機械学習を用いた画像認識システムを活用した管路欠陥の自動検出により、ユーザの欠陥確認作業の労力軽減! |
|
| 管渠 マネジメント |
【管口カメラ点検と展開広角カメラ調査及びプロファイリング技術を用いた管渠マネジメントシステム(H25)】 |
| 管口カメラで大きな異常を発見(スクリーニング)した後、異常箇所について展開広角カメラにより詳細な調査診断を行うことにより、日進量を向上させるとともに、調査コストを削減! 必要に応じて、管勾配を計測する傾斜計測や耐荷力を把握するための管路形状プロファイリングによる調査を追加で実施することにより、調査精度の向上や効率的な改築・修繕工法の選定が可能! |
|
| 管渠 マネジメント |
【展開広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法による管渠マネジメントシステム(H25)】 |
| 無停止走行で管内画像の取得が可能な展開広角カメラによるスクリーニング調査技術により、短期間で広範囲の調査が実施可能。日進量を向上させるとともに、調査コストを削減! 必要に応じて、非破壊かつ非開削で管体の耐荷力を定量的に計測可能な衝撃弾性波検査法による追加調査を実施することにより、効率的な長寿命化計画(改築計画)の策定が可能に! |
|
| 劣化点検・調査 | 【下水圧送管路における硫酸腐食箇所の効率的な調査技術(H28)】 |
| 腐食の危険性が高い箇所を優先的かつ確実に調査し、事故リスクの低減および維持管理の効率化に貢献! | |
| ICT活用型管路マネジメント | 【ICTを活用した総合的な段階型管路診断システム(H30)】 |
| 劣化予測システムによる点検・調査箇所の効率的な絞り込みから、点検直視型カメラによる詳細調査を必要とする箇所の特定まで、一連の流れを段階型システムとして解決します! 点検・調査結果の情報蓄積をタブレット端末を利用して直接入力することにより、効率的にデータの蓄積の実現が可能になります! |
|
| AI 解析 管内異常検知 |
【水位計と光ファイバー温度分布計測システムにAIを組合せた雨天時浸入水調査技術(R1)】 |
| ・低コストで測定可能な水位計により、対策優先ブロックを絞り込みます! ・ラインスクリーニング※により雨天時浸入水を検出し、詳細調査が必要な範囲を絞り込みます! ・AIを活用し、効率的な解析作業を実現します! |
|
| AI 解析 管内異常検知 |
【AIによる音響データを用いた雨天時浸入水検知技術(R1)】 |
| 晴天時と雨天時における下水道管内の音響変化に着目し,市販のボイスレコーダによる音響調査とAI を用いた解析手法を組み合わせ、安価で効率的に雨天時浸入水の有無を検知! |
|
| ▲TOP | |
| テーマ | 実証技術名(採択年度) | |
|---|---|---|
| ICTを活用した 浸水対策 |
【ICTを活用した浸水対策施設運用支援システム(H26)】 |
|
| リアルタイムに豪雨や排水区域内施設の水位状況等を把握し、高速シミュレーションにより浸水発生を予測 既設施設能力を最大限に生かした運転により浸水被害を削減 |
||
| 都市浸水対策 | 【都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術(H27)】 |
|
| 雨水貯留管など浸水対策施設の効果的、効率的な運転支援や住民への自助・共助活動を促進することで、浸水被害を軽減! | ||
| ▲TOP | ||
| テーマ | 実証技術名(採択年度) |
|---|---|
| 下水熱利用 | 【管路内設置型熱回収技術を用いた下水熱利用に関する実証研究(H24)】 |
| 下水道管渠へ管更生と熱交換器の同時施工により改築と熱回収システムを構築! 未利用エネルギーを冷暖房や給湯に利用し、コスト縮減、省エネルギーを実現! |
|
| 下水熱車道融雪 | 【ヒートポンプレスで低LCCと高COPを実現する下水熱融雪システム(H30)】 |
| 融雪の放熱部や下水熱の採熱部に高熱性能の材料を用いることで下水熱の効率的な利用が可能となり、さらに採熱設備の設置方法や熱源水の循環方法の工夫を重ねることで、従来技術のボイラ方式や電熱方式では達成困難であった低いLCCと高いCOPを達成! | |
| ▲TOP | |